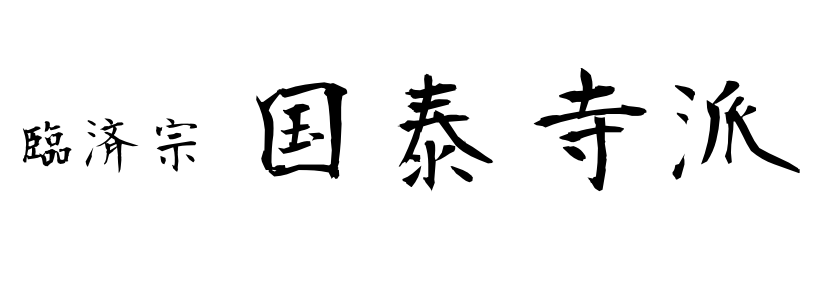『さしもぐさ』『へびいちご』『おにあざみ』『やえむぐら』『いつまでぐさ』、白隠禅師の著書の名です。植物、とりわけ雑草の類いの名称がつけられていることに特徴があります。
その意味は、雑草ですから、本来は無い方がいい“要らざる言”として自著をへりくだっているためといわれています。
そのように自著を雑草にたとえる白隠禅師、晩年には『草取歌』というものを著します。これは私たちの心にむくむくと沸き起こる煩悩・妄想を、田んぼに生えるいくら取ってもまた出てくる雑草にたとえて、その雑草を抜き、人間本来の生き方をするよう勧めるといった内容のものです。
「草を取るなら根をよく取りやれまたと意根をはやしゃるな」、『草取歌』の冒頭の一節です。
よく見ると「思う」という字にも、田んぼがあります。私たちはたしかに、心に思うことで心の田んぼに草を生やしてしまっているようです。
また「意根」という言葉は「遺恨」に通じます。心に張った草の深い“根”がそのうち“恨”みに転じていく。そんなときには、その根をよく取って二度と生えないようにしなければいけない。
草を取るための道具として古来より鎌があります。地面の草を鎌で根こそぎ取るように、心の煩悩の草を鎌の刃で取る。刃の心と書いて“忍”です。
忍は単に、たえしのぶことではなく、言偏(ごんべん)をつけると“認”となるように、認めていく、受け入れていくということです。それが刃の心で、自ずと心の草が取れていくということになります。
ノートルダム清心学園理事長を勤められた渡辺和子さん(1927~2016)の言葉に
もしあなたが誰かに期待した
ほほえみが得られなかったら
不愉快になる代わりにむしろ
あなたからほほえんでごらんなさい
実際ほほえみを忘れた人ほど
あなたからのそれを
必要としている人はいないのだから
というものがあります。他人に無愛想にされるとき自分の機嫌も悪くなる、誰でも心当たりのあることだと思いますが、そんなときどうするか?
それは、自分の心に生えた不愉快という草を根っこから取るしかありません。取るということは、刃の心で草を取って、認めていくことと申しましたが、渡辺さんの文章では、それは「あなたからほほえんでごらんなさい」となります。
また「忍ぶ」は「偲ぶ」です。人を思うことにつながります。
不愉快という草を、こちらから微笑むということで転換していく、そうして自分も活かし、周りも活かしていく。
うちのお寺の周辺にも田んぼが広がっていますが、草の生えていない田んぼはそれを見るだけで清々しい気持ちになります。
それと同じく、本当に自分の心の草取りをしている人を見るならば、その人の顔や姿を見ただけで、救われていくのだと思います。
皆さんも私もお互いに、そんな心の草取りのできる人になれるよう日々勤めたいものです。
※お話
臨済宗連合各派布教師
本派吉祥寺住職 山田真隆師
*法話のご依頼を受け付けています。
法要やセミナーなどで、
法話を聞きたいと思われる方は
本山に直接お問い合わせされるか、
kokutaijiha@kokutaiji.info
までご連絡ください。
*本法話をご利用になる場合は、
上記メールアドレスまで
ご連絡ください。
無断転載を禁じます