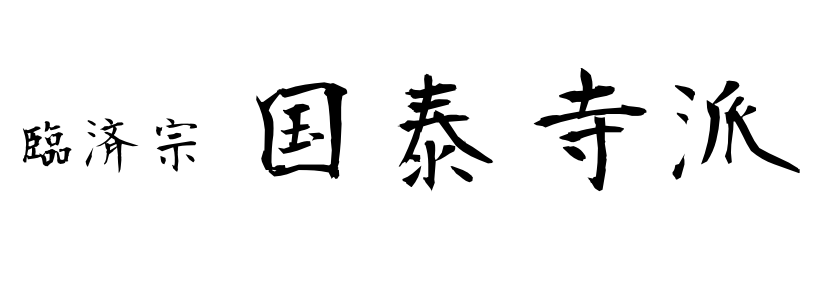人は仕事や生活がうまくいっているときには、日常の些細な問題も気になりませんが、うまくいかなくなると途端に、その原因を見つけたくなります。そしてその原因を他人にもとめることはあっても、なかなか自分を省みるということはできないもの。そんな時こそ、やはり他人ではなく、自分の生き方を問うべきだと思います。
人間としてどう生きたらいいのか?を問うことは、言い換えれば「いま」をどうとらえるかにつきます。「いま」を問うことは生きている者にしかできないことだからです。 ですから、私たちは誰もがそのままで、過去でもなく、未来でもなく、「いま」を生きています。だから「いまを生きる」というのは、すでにみなさんがそうであります。ですが本当の意味で「いまを生きて」いるかが問題です。
今から一一五〇年前に亡くなられた臨済宗の祖・臨済義玄禅師は「いまを生きる」ことを「即今目前聴法底の人」(『臨済録』示衆)と示されました。
「いまを生きる」ということは、「まさに今、私の目前で説法を聴いている人」であることに他ならない、もっと簡単な言葉で言い換えると「即今」は「いま」、「目前」は「ここ」、「聴法底の人」は「わたし」となります。ですから「いま」をとらえるということは、必ず「ここ」と「わたし」も同時にとらえるということです。
私たちが生きているのは、「わたしがいまここにいる」以外に無いと気付くことだといえます。
詩人・まどみちおさん(一九〇九~二〇一四)の詩で「ぼくがここに」があります。
ぼくがここにいるとき
ほかのどんなものも
ぼくにかさなって
ここにいることはできない
もしもゾウがここにいるならば
そのゾウだけ マメがいるならば
その一つぶのマメだけ しか
ここにいることはできない
ああこのちきゅうのうえでは
こんなにだいじに
まもられているのだ
どんなものがどんなところに
いるときにも
その「いること」こそが
なににもまして
すばらしいこととして
まどさんはこの詩のなかで、「わたしがいまここにいる」ことの有り難さ、すばらしさを謳います。「ほかのどんなものも、ぼくにかさなって、ここにいることはできない」ことは、「わたしがいまここにいる」ことについて、交換がきかない、比較ができない、ということです。誰もがその人の替わりはできない。その人と比べることはできない、それを「かけ替えの無い」ともいいます。
そんなかけ替えのない存在は、わたしだけでなく、ゾウでも一つぶのマメでも同じだということです。わたしというものが、かけ替えがない存在だと気付けば、それと同じように、わたし以外のもののかけ替えの無さにも、気付くはずです。
そしてまた有り難いことに「どんなものが、どんなところに、いるときにも」「こんなにだいじにまもられている」という私たちであります。そうやって私たちが「いること」がすばらしくない訳がありません。
「わたしがいまここにいる」が本当にわかる人は、自分と同じように「いまどこかにいるだれか」を大切にできる生き方ができるのです。それが「いまを生きる」という人間の生き方ではないでしょうか。
詩人・高田敏子さん(1914~1989)の「雨の日の花」という詩があります。
雨がふっている
花は咲いている
花の上に落ちる雨
悲しんでいるのは
雨だった
花をよけて
雨はふることはできない
花は咲いている
雨の心をいたわり
うけとめて
花びらに
花の心を光らせて
花は
咲いている
雨は精一杯降っている、だから余力がなく花をよけられない。
同じように花も精一杯咲いている、だから雨をよけられない。
だけど雨と花はけんかをするのではなく、
雨は花を思いやり、
花は雨を思いやり、
お互いに精一杯いまを生きているからこそ、
お互いのかけ替えの無さが感じられる。
大切に思いやる生き方ができることを、この詩は教えてくれているようです。
茶道を大成した千利休居士の孫に千宗旦という人がいます。豊臣秀吉に千家が取りつぶされた後、その難しい千家の再興を成し遂げたのがこの宗旦居士です。 ある日、宗旦居士と親交のある京都のあるお寺の和尚さんが、寺の庭に咲いた珍しい椿の花を一枝、小僧さんに持たせて宗旦居士の元に届けさせました。
椿の花は落ちやすいもの。小僧さんは道中気をつけていたものの、途中で花を落としてしまいました。小僧さんは正直にそのことを宗旦居士に伝えて自分の失敗を詫びました。すると宗旦居士はにこやかに笑って、それを許し、その小僧さんを茶席に招きました。
宗旦居士はあらかじめ準備していた床の間の掛け軸を外して、代わりに竹の筒の花入れに小僧さんが落としてしまった椿を投げ入れ、その花入れの下に落ちた椿の花を置いて、抹茶を点て、「ご苦労様でした」と小僧さんの労をねぎらって、寺へ帰したということです。(井伊直弼『閑夜茶話』)
精一杯生きて花をつけた椿、その椿を精一杯運んだ小僧さん、どちらも「いまを生きて」いる交換のきかないものです。だからこそ、その椿も小僧さんも大切にして活かしきった宗旦居士。こんな話が残っている宗旦居士という方は、やはり「いまを生きる」ことが本当にわかっていた方ではないかと思います。
是非私たちもこんな話のような生き方をしてみたいとは思いませんか。
白隠慧鶴禅師は「わたしがいまここにいる」ことを「当処即ち蓮華国此の身即ち仏なり」と『坐禅和讃』で説かれています。本当に「いま」に気がつけば、「ここ」はお浄土、「わたし」は仏ですよ、と見ることができます。その「いま・ここ・わたし」をこの臨済・白隠両祖師の遠諱を機に見直してみるのはいかがでしょうか。
※お話
臨済宗連合各派布教師
本派吉祥寺住職 山田真隆師
*法話のご依頼を受け付けています。
法要やセミナーなどで、
法話を聞きたいと思われる方は
本山に直接お問い合わせされるか、
kokutaijiha@kokutaiji.info
までご連絡ください。
*本法話をご利用になる場合は、
上記メールアドレスまで
ご連絡ください。
無断転載を禁じます